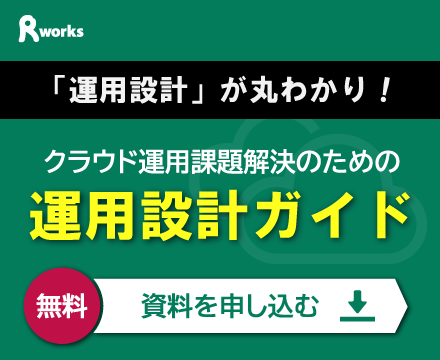目次
Azure で実現するサーバー冗長化の主要技術も紹介
サーバーは、企業の業務システムや Web サービスを安定的に提供するための基盤です。サーバーに重大な障害が発生すると、業務システムや Web サービスなどを継続して提供することが難しくなり、顧客からの信頼を失うリスクが高まります。こうした事態を防ぐための重要な対策の一つが「サーバーの冗長化」です。
本記事では、サーバーを冗長化する目的や重要性、検討する際のポイントを解説します。Azure で実現できるサーバ冗長化の方法や技術なども紹介しますので、参考にしてください。
1. サーバーの冗長化とは
サーバーの冗長化とは、万が一サーバーに障害が発生しても業務を止めないように、同等の機能を持つ複数のサーバーを用意し、可用性を高める構成のことです。
「冗長」という言葉には「余分」「無駄」などの意味が含まれています。IT 分野における冗長化は、サーバーやネットワーク、ストレージなどの構成要素を多重化することを指すのが一般的です。
冗長化と二重化の違い
冗長化と混同しやすいのが「二重化」です。二重化は、同じ機能を持つ機器を 2 台用意し、どちらか一方が故障したときにもう一方で代替する構成です。一方の冗長化は、2 台以上の構成や処理の分散なども含めた、より広い概念を指します。
サーバーを冗長化する代表的な構成2つ
サーバーを冗長化する代表的な構成は、アクティブ・スタンバイ、アクティブ・アクティブの 2 つです。それぞれの詳細は、以下の記事をご覧ください。
2. サーバーを冗長化する目的・重要性
続いて、サーバーを冗長化する目的・重要性について詳しく解説します。
システムの可用性を高める
サーバーの冗長化により、システムの可用性を高めることが可能です。たとえば、単一構成のサーバーでは、重大な障害が発生した際、サービス停止に至るケースがあります。冗長構成をとることで、別のサーバーが処理を引き継ぐため、サービスの提供を継続できます。
さらに、サーバーを冗長化すると、業務に影響が出ないようにパッチ適用やメンテナンスなどを実施することも可能です。ユーザーへの影響を最小限に抑えつつ、安定したサービス運用を実現できます。
障害時の影響を軽減する
サーバーの故障やトラブルを完全に回避することは困難です。しかし、あらかじめサーバーを冗長化しておけば、障害発生時の影響範囲を最小限に抑えられます。複数台のサーバーを事前に用意することで、 1 台のサーバーが故障してもシステム全体を停止させず、継続的な稼働が可能です。
さらに、冗長構成を採用すると、システムの目標復旧時間( RTO : Recovery Time Objective )を短縮し、障害に強いインフラ運用を実現できます。なお、 RTO の詳しい意味や RPO ( Recovery Point Objective =目標復旧地点)との違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
BCP対策を実現する
BCP ( Business Continuity Plan )とは、災害やシステム障害などの緊急事態が発生した際も、事業を継続・早期復旧できるようにするための事業継続計画です。サーバーの冗長化は、 BCP 対策の一環としても有効です。
たとえば、異なる拠点にスタンバイ用のサーバーを配置することで、拠点全体が被災するような大規模障害が発生しても、業務を継続するための体制を迅速に構築できます。
3. Azureで実現するサーバー冗長化の主要技術
Azure には、可用性の高いシステムを構築するための多様なサービスが用意されています。これらを適切に組み合わせることで、障害に強いインフラの設計が可能です。
ここでは、 Azure で実現できるサーバー冗長化の技術を 3 つ紹介します。
Azure Virtual Machinesにおける可用性セット・可用性ゾーンの活用
可用性セットは、 Azure の単一データセンター内に存在する複数のサーバーラックに仮想マシンを分散配置する仕組みです。ハードウェアの故障や定期メンテナンスの影響が仮想マシン全体に波及するリスクを低減できます。
一方、可用性ゾーンは、物理的に完全に分離された複数のデータセンター間でリソースを冗長化する仕組みです。あるゾーンが自然災害や障害で停止しても、ほかのゾーンに配置されたリソースで稼働し続けることが可能です。
Azure Virtual Machines は、 Azure が提供する仮想サーバーサービスであり、柔軟な構成と高い拡張性を備えています。 Azure Virtual Machines において可用性セットや可用性ゾーンを活用することで、システムの停止リスクを最小限に抑えられます。さらに、ビジネス継続性の高いインフラ構成を実現できるでしょう。
Azure Load Balancerによるトラフィック分散
Azure Load Balancer は、複数の仮想マシンやサービス間でネットワークトラフィックを自動的に分散させるロードバランシングサービスです。特定のサーバーにアクセスが集中して負荷が偏ることを防ぎ、サービスの安定性と応答性の向上に寄与します。
仮想マシンの一部に障害が発生した場合でも、正常に動作しているほかのインスタンスに自動で切り替えることで、サービス停止を回避できます。
Azure Site Recoveryを活用したBCP対策
Azure Site Recovery は、 DR (ディザスタ・リカバリ)を実施できるサービスです。本番環境で障害や災害が発生した場合でも、待機系へのフェールオーバー(自動切り替え)を実行でき、計画的な復旧テストも容易におこなえます。
Azure Site Recovery を活用すれば、リージョン障害や大規模災害を想定した冗長構成を構築することが可能です。 BCP (事業継続計画)を実現する際にも重要な役割を果たします。
4. サーバーの冗長化を検討する際のポイント
サーバーの冗長化を検討する際は、以下の 2 つのポイントを確認しましょう。
システムの可用性要件を把握する
まずは、業務上システムがどの程度の時間停止を許容できるのか( RTO )、データ損失の許容範囲はどの程度か( RPO )といった指標をもとに、必要な冗長構成のレベルを判断しましょう。
たとえば、 EC サイトや基幹業務システムのように常時稼働が求められるシステムであれば、可用性ゾーンを用いた冗長構成や、複数の地域(リージョン)に分散配置するマルチリージョン構成といった高可用性を実現する構成が求められます。
一方で、リアルタイムな業務進行に直結しない定期的なバッチ処理など、停止の許容度が高いシステムであれば、単純なスタンバイ構成でも十分に対応できるでしょう。
冗長化にかかるコストを算出・比較する
冗長化はシステムの信頼性向上に貢献する一方で、追加のコストが発生する点に注意が必要です。仮想マシンやストレージを複数用意する場合、その分のインフラ費用や運用コストが増加します。また、構成の複雑化に伴い、設計・管理にかかる工数や人的負担も増えるでしょう。
「どのレベルの可用性が必要か」「その実現にどれだけのコストがかかるか」を整理し、費用対効果の観点から構成を最適化することが重要です。
5. まとめ
今回は、サーバーを冗長化する目的や重要性、検討する際のポイントについて解説しました。サーバーの冗長化は、システムの可用性を高め、障害発生時の影響を最小限に抑えるために不可欠な取り組みです。Azure には、可用性セットや可用性ゾーン、 Azure Load Balancer 、 Azure Site Recovery など多様な冗長化技術が備わっており、要件に応じて柔軟な構成を実現できます。
RW では、 Azure 導入支援サービス を提供しており、お客様の環境に合わせた最適なご提案が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
Azure の導入を相談したい


資料ダウンロード
課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら
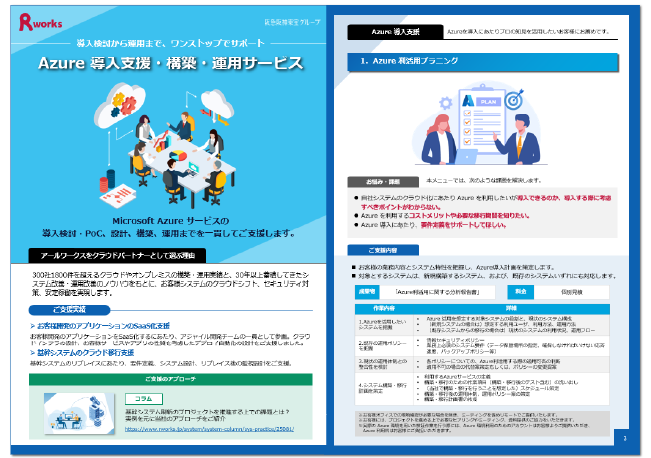
-
-
Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ
Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。
Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。
-
Microsoft Azureを利用したシステムの設計・構築を代行します。お客様のご要件を実現する構成をご提案・実装いたします。
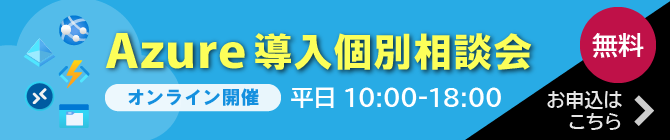
Contactお問い合わせ
お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。







 03-5946-8400
03-5946-8400