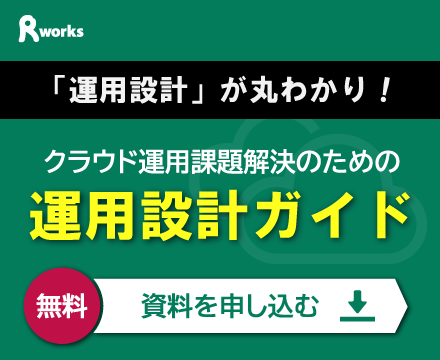目次
OSSライセンスを正しく理解してOSSを使用しよう
OSS とは Open Source Software の略で、ソースコードが公開され、ライセンス条件を守れば誰でも利用できるソフトウェアを指します。 OSS ライセンスには GPL や MIT など複数の種類があり、利用や配布のルールがそれぞれ異なる点に注意が必要です。本記事では OSS ライセンスの概要、種類、 Azure で使用できる OSS ライセンス、 使用上の注意点について解説します。
1. OSSライセンスとは
OSS とは、ソースコードを誰でも入手可能であり、ライセンス条件を遵守することで活用できるソフトウェアです。
OSS は一般的に無料で利用できますが、使用者がライセンス条項を遵守することが前提となります。 OSS ライセンスには複数の種類があり、複製可否や再頒布(さいはっぷ)時のソースコード公開、派生物の取り扱いといった点に違いがあるため注意が必要です。再頒布とは、著作物を改変、複製して二次配布することであり、派生物とは改変や再頒布した二次的著作物を指します。
2. OSSライセンスの種類と特徴
OSS ライセンスは大きく以下の3種類に区分できます。
| 分類 | 複製・再頒布・改変 | ソースコードの開示 | 代表的なライセンス |
|---|---|---|---|
| コピーレフト型 | 可能 | OSS 、独自プログラム双方の開示が必要 | GPL 、 AGPL |
| 準コピーレフト型 | 可能 | OSS 部分の開示のみ必要(独自プログラムは不要な場合が多い) | LGPL 、 MPL |
| 非コピーレフト型 | 可能 | 不要 | Apache License 2.0、 MIT 、 BSD |
コピーレフト( Copyleft )は、オープンソースソフトウェア( OSS )のライセンスにおける概念です。ソフトウェアの自由な利用、改変、再頒布を保証する一方で、派生物も同じライセンスで公開することを義務付けています。
コピーレフト型と準コピーレフト型の違いは、開示するソースコードの範囲です。両者とも OSS 部分のソースコード開示は必要ですが、準コピーレフト型では独自に開発したプログラムのソースコードは開示しなくてよい場合が多く見られます。ただし、ライセンスによってはソースコードまたはオブジェクトコードの開示が必要なため、事前に確認する必要があります。
ライセンスごとの特徴は以下のとおりです。
| ライセンス | 公開義務 | 特徴 | 再配布 | 代表的な使用例 |
|---|---|---|---|---|
| GPL | すべての改変を 公開 |
強制力の強い コピーレフト |
ソースコードの公開必須 | Linux 、 MySQL 、 WordPress |
| AGPL | GPL +ネットワーク提供部分も公開 | SaaS 向けに厳格化 | ソースコードの公開必須 | SaaS 向けソフトウェア ( Nextcloud 、 OPEN edX など) |
| LGPL | ライブラリ改変のみ公開 | ライブラリ用、 リンク利用は自由 |
条件付き公開 | glibc 、 OpenOffice |
| MPL | 改変したファイル のみ公開 |
コピーレフトは ファイル単位 |
条件付き公開 | Firefox 、 Thunderbird |
| Apache License 2.0 | ソース公開不要、 著作権表示のみ |
特許権許諾あり、商用向け | 自由 | HTTP Server 、 Hadoop |
| MIT | ソース公開不要、 著作権表示のみ |
簡潔で 自由度が高い |
自由 | React 、 Ruby on Rails |
| BSD | ソース公開不要、 著作権表示のみ |
MIT に類似、 歴史が古い |
自由 | FreeBSD 、 PostgreSQL |
3. Azure上で利用できるOSS
Azure は多くの OSS (オープンソースソフトウェア)に対応しており、 OSS ライセンスの規約にもとづき使用できます。たとえば、 Linux ディストリビューション、 MySQL や PostgreSQL といったデータベース、 Apache や Nginx といった Web サーバー、 OSS として公開されている開発言語が使用可能です。
OSS 利用時には、利用者自身がライセンス条件を遵守しなければなりません。 Windows や Oracle DB のような OSS ではない商用製品は個別にライセンス体系があり、そもそも OSS ライセンスの対象ではない点に注意が必要です。
Azure で利用できる OSS の一部は以下のとおりです。
| 種類 | 利用例 |
|---|---|
| OS( Linux ) | Red Hat Enterprise Linux 、 Oracle Linux 、 Debian GNU / Linux など |
| Database サーバー | MySQL 、 PostgreSQL など |
| Web サーバー | Apache HTTP Server 、 NGINX など |
| 機械学習 | TensorFlow 、 PyTorch など |
| コンテナ | Docker 、 Kubernetes など |
Azure で使用できる OSS は、独自にインストールして導入するほか、 Azure Marketplace 経由でも入手できます。
4. OSS使用上の注意点
OSS を使用する際は、ライセンスやコンプライアンスについて理解したうえで、再頒布やソースコードの公開を行う必要があります。ここでは、 OSS を使用するうえでの注意点を解説します。
ライセンスごとの義務を理解する
OSS には GPL 、 AGPL 、 LGPL 、 MIT 、 Apache License 2.0、 BSD などさまざまなライセンスがあり、条件や制約事項はそれぞれ異なります。たとえば、 GPL や AGPL はコピーレフトの強制力が高いのに対し、 MIT や BSD は非コピーレフト系ライセンスに分類されます。著作権表示やライセンス文言を残せば再頒布が可能であり、ソース公開義務は課されません。 OSS を使用する際には、 OSS ライセンスの違いと義務を理解する必要があります。
OSS利用時の再頒布条件を確認する
OSS を改変しない場合と、改変や再頒布する場合では条件が異なります。 GPL や AGPL はソースコードを改変した場合、再頒布時にソースコード公開が必須であるのに対して、 MIT や BSD は自由に再頒布が可能です。ライセンスで果たすべき義務と同様に再頒布条件にも注意する必要があります。
商用利用やSaaS提供時のコンプライアンスを考慮する
OSS を商用製品や SaaS サービスに組み込む場合、法令順守やコンプライアンスを意識する必要があります。特に AGPL は、ネットワーク越しで提供されるサービスもソース公開義務が発生するため、 SaaS でサービスを提供する場合は慎重に扱わなければなりません。
OSSライセンス違反は法的リスクがある
OSS ライセンスに違反した場合、著作権侵害として訴訟や損害賠償につながるおそれがあります。特に、商用利用や外部公開、クラウド上での OSS 利用時は注意しなければなりません。 企業が OSS を使用する際は、ライセンスの詳細を確認し、チェック体制を整備して違反リスクを最小化することが重要です。
5. まとめ
OSS ライセンスとは OSS を使用する際のライセンス形態です。 OSS ライセンスには GPL 、 AGPL 、LGPL といったさまざまな形態があり、 Azure ではほぼすべての OSS を使用できます。
OSS を使用する際は、 OSS ライセンスを遵守することが求められます。 OSS ライセンスはライセンス体系によって再頒布時のソースコード公開、派生物の取り扱いに関する条件が異なる点に注意が必要です。
Rworks 社は OSS に関する深い知見と経験があります。ぜひ気軽にお問い合わせください。
Azure の導入を相談したい


資料ダウンロード
課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら
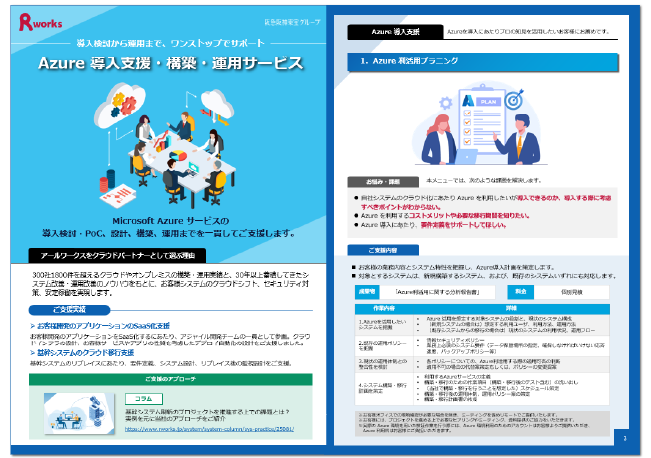
-
-
Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ
Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。
Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。
-
Microsoft Azureを利用したシステムの設計・構築を代行します。お客様のご要件を実現する構成をご提案・実装いたします。
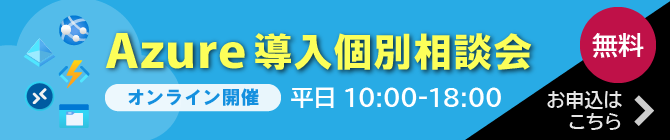
Contactお問い合わせ
お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。







 03-5946-8400
03-5946-8400