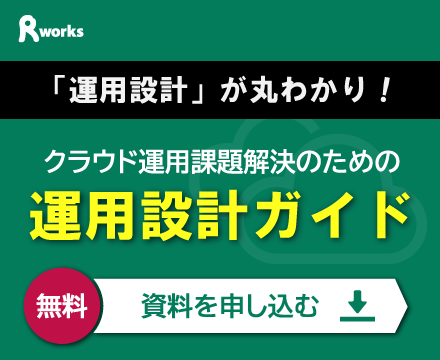目次
システム移行で活用できる Azure サービスも紹介
システム移行は、老朽化したシステムの刷新や DX 推進に欠かせない重要なプロセスです。近年では、クラウドへの移行を検討する企業が増えています。しかし、方式の選定や手順を誤ると、コストや工数が膨らみ、業務に深刻な影響を及ぼしかねません。本記事では、システム移行の主な方式や具体的な手順、システム移行を成功させるポイントについて解説します。
1. システム移行とは?
システム移行とは、既存のシステムを別の環境へ移行する作業です。システムを移行する際は、トラブルを防止するための綿密な計画が欠かせません。計画どおりに進まないと、予算や時間、人的リソースが大幅に増えるおそれがあります。
システム移行が必要なケース
システム移行が必要となる主なケースは下記のとおりです。
| システム移行が必要なケース | |
|---|---|
| ハードウェアの保守期限切れ | 古いサーバーやストレージ機器の保守期限が切れる。 |
| OS のサポート終了 | OS のバージョンが古くなり、セキュリティパッチや開発元のサポートを受けられなくなる。 |
| システムの統合 | 企業合併や組織再編により、複数のシステムをひとつにまとめる必要がある。 |
| DX やコスト削減 | DX や運用保守コストの削減の一環として、オンプレミス環境をクラウド環境へ移行する。 |
| 利用規模の拡大による性能不足 | ユーザー数や処理量が増加し、既存システムではパフォーマンスが不足する。 |
システム移行のパターンはさまざま
システム移行には下記のようなパターンがあります。- オンプレミスから新しいオンプレミスへシステムを更新する
- オンプレミスからクラウドに移行する
- クラウドからオンプレミスに移行する(オンプレ回帰)
オンプレミスとは、自社に設置したサーバーやストレージ、ネットワーク機器を利用してシステムを運用する方式です。セキュリティ対策を自社で直接管理できる点が強みですが、日々の運用保守や機器の入れ替えに高額なコストが発生しやすいデメリットもあります。近年では、コスト削減や DX などを目的に、オンプレミスからクラウドへ移行する企業が増えています。
クラウドとは、クラウド事業者が提供するサービスをインターネット経由で利用する方式です。多くのクラウドサービスは従量課金制を採用しているため、初期費用を抑えられ、利用状況に応じて柔軟に拡張できるメリットがあります。ただし、セキュリティ要件や、想定以上に膨らむコスト最適化の観点から、近年ではクラウドから再びオンプレミスへ移行する動きも一部で見られます。
2. システム移行の主な方式
システム移行の主な方式を 4 つ紹介します。
一括移行方式(ビッグバン方式)
現行のシステムを新システムへ一括移行する方式です。それぞれのシステムを並行して運用する必要がなく、コストや手間を抑えられる点がメリットです。ただし、移行に失敗するとシステム全体に大きな影響が及ぶ点や、一定期間のサービス停止が発生する点がデメリットとして挙げられます。
移行コストを抑えたい企業や、長期休暇を活用して切り替えたい企業などに適しています。
段階移行方式
業務や機能ごとに段階的に移行する方式です。まとまった停止期間を確保せずに移行を進められますが、複数回の移行作業が必要となり、手間やコストが増える傾向があります。
大規模なシステムを利用しており一度に移行するのが難しい企業や、トラブル時の影響を局所化したい企業などに適しています。
並行運用方式(パラレル方式)
現システムと新システムを一定期間並行して運用・検証する方式です。新システムに問題が発生しても現行システムで業務を継続でき、移行リスクが低減されますが、追加のコストや工数がかかります。
移行後のリスクを最小限に抑えたい企業や、予算や人員に余裕がある企業などにおすすめです。
パイロット移行方式
影響が少ない一部の業務から先行して移行し、検証してから全体へ展開する方式です。先行導入で問題点を把握できるため、移行時のリスクを抑えられます。ただし、検証や段階展開に時間がかかり、移行が長期化する課題があります。
システム移行を慎重に実施したい企業や、十分な移行期間を確保できる企業などにおすすめです。
3. システム移行の具体的な手順
ここでは、システム移行の具体的な手順を解説します。各工程で活用できる Azure のサービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
現行システムの調査
まずは、現行システムに精通した担当者をチームに加え、設計書や仕様書の有無、OS種別やバージョン、データ量、最新のバックアップ状況などを網羅的に洗い出しましょう。
Azure Migrate は、オンプレミスのサーバーやアプリケーション、データベースなどを Microsoft Azure へ移行するプラットフォームです。現行システムの検出や評価から、 Azure への移行計画策定、移行の実行・監視までを一元的にサポートできます。
データの整理
移行対象となるデータを整理しましょう。新システムで必要なデータのみを移行することで、作業の手間やコストを抑えられます。
Azure Data Factory は、オンプレミスやクラウドに分散しているさまざまなデータソースからデータを収集し、変換・統合できるデータ統合サービスです。移行対象のデータを効率的に抽出できます。
移行計画書の作成
移行方針やスケジュール、移行対象データ、使用ツール、リスク対策、体制などを整理し、関係者間で合意形成を図ることが重要です。また、この段階で利用マニュアルを整備し、現場担当者が新システムをスムーズに運用できるよう準備しておきましょう。
移行リハーサルの実施
次に、移行リハーサルを実施します。本番に近い環境で移行作業の検証を実施することがポイントです。
移行作業を実施
移行リハーサルが完了したら、本番環境で移行作業を行います。ミスを防ぐために複数名で作業を実施し、作業ログも必ず記録しましょう。
移行後テストと安定稼働モニタリング
新システムのテストを実施します。新システムを利用して1日の業務サイクルを実際に回し、業務が問題なく行えるかを確認します。
また、テスト後の安定稼働を確認・維持するためには、継続的なモニタリングが欠かせません。 Azure Monitor を利用すれば、システムの稼働状況やパフォーマンスをリアルタイムで監視し、異常を早期に検知することが可能です。
4. システム移行を成功させるためのポイント
システム移行を成功させるためには、下記のポイントを押さえることが重要です。
スケジュールに余裕を持たせた移行計画を立てる
システム移行では不測の事態が発生しやすく、作業の手戻りや予期しないトラブルによって計画が延びることがあります。手戻りを想定し、余裕のあるスケジュールを組むことが重要です。
新システムの運用担当者への教育も並行して実施する
移行作業が無事に完了しても、担当者が操作に不慣れであれば業務に支障をきたします。操作説明会やマニュアルの整備を行い、運用体制を整えておきましょう。
リスク管理とロールバック計画を策定する
移行中に重大なトラブルが発生した場合、速やかに旧システムへ戻す仕組みがあれば、業務停止の影響を最小限に抑えられます。想定されるリスクを洗い出し、事前に対応策を準備しておくことが重要です。
Azure Backup を利用することで、仮想マシンやデータベース、ファイルをクラウド上にバックアップできます。移行作業で問題が発生しても、バックアップから迅速に復旧できるでしょう。
Azure Site Recovery を利用すれば、オンプレミス環境を Azure にリアルタイムでレプリケーションすることが可能です。万一トラブルがあった場合もフェールバック機能で旧環境に戻せるため、移行リスクを軽減できます。
5.まとめ
システム移行は、企業の競争力や将来の成長を左右する重要なプロジェクトです。しかし、計画立案からデータ移行、セキュリティ対策やコスト最適化までを自社だけで完結させるのは容易ではありません。
Rworks では、 Azure 導入支援サービスを提供しており、要件定義から設計・構築・運用までを一貫してサポートすることが可能です。システム移行をご検討の企業は、お気軽にご相談ください。
Azure の導入を相談したい


資料ダウンロード
課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら
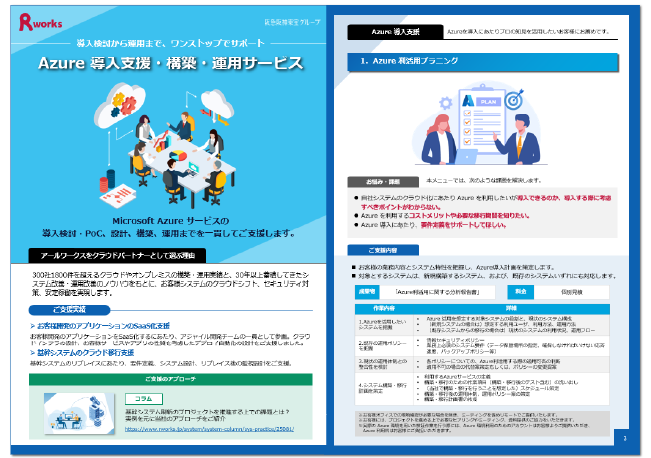
-
-
Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ
Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。
Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。
-
Microsoft Azureを利用したシステムの設計・構築を代行します。お客様のご要件を実現する構成をご提案・実装いたします。
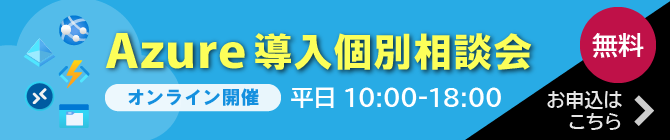
Contactお問い合わせ
お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。







 03-5946-8400
03-5946-8400