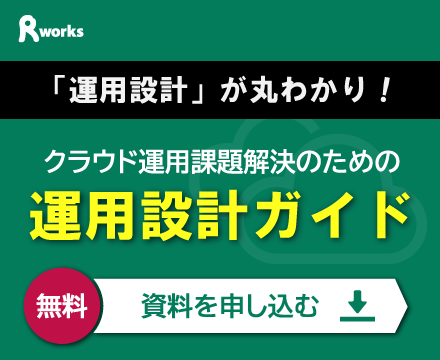目次
冗長構成を設計する際の注意点とは?
サーバーやネットワークなどの IT インフラは、障害や災害といった予期せぬトラブルによって停止するリスクがあります。 IT インフラが停止すると、業務の中断を余儀なくされ、売上の損失や顧客からの信頼低下につながりかねません。こうしたリスクを最小限に抑えるために重要となるのが「冗長構成」です。
本記事では、冗長構成の概要や対象領域、 Azure サービスを活用した実装方法について解説します。冗長構成の運用・管理のポイントも紹介しますので、最後までご覧ください。
1. 冗長構成の基本概念
はじめに、冗長構成の基本概念について解説します。
冗長構成とは
冗長構成とは、同一の性能や構成を持つサーバーやネットワーク機器を複数用意し、メイン側でトラブルが発生した際にも稼働を継続できるようにする構成です。冗長構成は、サーバーやネットワーク、ストレージ、データベースなど、さまざまな領域で実現できます。
冗長化の目的と必要性
冗長化とは、性能・構成・データ内容が同一の予備(スペア)を用意することです。システムや設備に障害が発生すると、障害の程度によっては業務を停止せざるを得なくなります。復旧までの時間が長引くほど、売上損失や顧客信頼の低下といった影響が大きくなるでしょう。冗長化をおこなうことで、障害発生時も業務を継続でき、被害を最小限に抑えられます。
代表的な冗長構成
代表的な冗長構成は、アクティブ・スタンバイ、アクティブ・アクティブの 2 つです。それぞれの特徴や違いについては、以下の記事をご参照ください。
2. 冗長構成の対象領域と実装方法
続いて、冗長構成の対象領域と Azure を用いた実装方法を詳しく見ていきましょう。
サーバー
サーバーは、前述のアクティブ・スタンバイやアクティブ・アクティブ構成で冗長化できます。また、アクティブ・スタンバイ構成には、スタンバイ機の稼働状態に応じて、ホットスタンバイやコールドスタンバイといった方式が存在します。
ホットスタンバイは、予備のサーバーを常に起動させ、本番機とほぼ同じ状態に保つ方式です。障害発生時の切り替え時間が短く、業務停止のリスクを最小限に抑えられますが、常時稼働させるためコストが高くなる傾向があります。コールドスタンバイは、予備機を通常時は停止させ、障害発生時に起動して処理を引き継ぐ方式です。コストは低く抑えられますが、切り替えや起動に時間がかかる点がデメリットです。
Azure Virtual Machines を利用すれば、物理的・論理的に分離されたサーバー配置が可能となります。さらに、 Azure Load Balancer を併用することで、トラフィックを分散し、障害時に正常なサーバーへ自動的に切り替えられます。
ネットワーク
ネットワークの冗長化は、ネットワーク機器に対する冗長構成に限らず、 OSI 参照モデルの各レイヤーに応じて異なる手法が用いられるため、幅広い対策が存在します。代表的な方式が、 STP ( Spanning Tree Protocol )とリンクアグリゲーションの 2 つです。
STP は、ネットワーク内でループが発生しないよう経路を制御しつつ、障害時には迂回経路を自動的に有効化するプロトコルです。リンクアグリゲーションは、複数の物理リンクを束ねて 1 本の論理リンクとして扱い、帯域の拡張と障害時の自動切り替えを同時に実現します。
Azure 環境では、仮想ネットワーク( VNet )や ExpressRoute などを活用することで、複数の可用性ゾーンや物理回線を活用した L2 〜 L3 レベルの冗長構成を構築できます。さらに、 Azure Firewall や Application Gateway を組み合わせれば、 L3 以上のレイヤーにおいてもセキュリティと可用性を両立したネットワーク冗長化を実現可能です。
ストレージ
ストレージは、企業にとって最も重要な資産であるデータを保管するための基盤です。データ消失を防ぐための冗長構成は不可欠といえるでしょう。代表的な技術としては、ストレージ機器自体の冗長構成に加え、 RAID ( Redundant Array of Independent Disks )などが挙げられます。RAID は複数の物理ディスクにデータを分散保存し、一部のディスクが故障してもデータを保持できる仕組みです。
Azure では、保存するデータの種類に応じてさまざまなストレージサービスが提供されています。代表的なサービスは、 Azure Files や Azure Disk Storage 、 Azure Blob Storage などです。
データベース
データベースは、顧客情報や売上データ、取引履歴などの重要な業務データを管理するため、可用性と整合性の確保が求められます。冗長化の方式として代表的なのが、レプリケーションです。レプリケーションとは、データを複製して複数のサーバーに保持し、障害発生時は別サーバーから提供する方式を指します。レプリケーションの構成として代表的なのが、マスター・スレーブとマルチマスターの 2 つです。
マスター・スレーブは、 1 台のマスターサーバーがデータの書き込み処理を担当し、スレーブサーバーがマスターのデータを複製して読み取り専用で保持する方式です。一方、マルチマスターは、複数のサーバーがそれぞれマスターとして機能し、どのサーバーでもデータの書き込みが可能な方式を指します。
Azure SQL Database を利用すれば、業務データの保護と高可用性を同時に実現できます。
3. 冗長構成を設計する際の注意点
冗長化を検討する際は、まずシステムの影響度を評価する必要があります。RTO (目標復旧時間)や RPO (目標復旧地点)に基づき、停止による影響や損害が大きいシステムから優先して冗長化を進めることが重要です。
具体的には、基幹システムや決済系システムなど、稼働停止が企業全体の業務や支払業務に直接影響するサーバーやストレージ、ネットワークなどが該当します。また、近年ではインターネット接続が業務遂行に不可欠となっています。オンラインサービスを提供していない企業であっても、インターネットの出入口設備を冗長化し、接続の安定性を確保することが望ましいでしょう。
4. 冗長構成の運用・管理
ここでは、冗長構成の運用・管理のポイントや注意点を解説します。
監視・メンテナンスの重要性
冗長構成の有効性を維持するためには、本番環境だけではなくスタンバイ機についても、各機器やサービスの稼働状況を常時監視し、異常を早期に検知することが重要です。監視ツールやアラート設定を活用し、障害の兆候を事前に把握できる体制を整えましょう。
また、スタンバイ機や冗長化された環境に対してもパッチ適用やアップグレードを必ず実施し、本番と同等の環境を維持する必要があります。これにより、障害発生時にバージョン差異などが原因で切り替えができないといった事態を防ぐことが可能です。
障害発生時の対応策
障害時には迅速な切り替えと復旧が求められます。そのため、復旧を優先すべきシステムを特定し、システムごとの目標復旧時間( RTO )を事前に決定することが重要です。
さらに、対応手順の全従業員への周知と、定期的な訓練の実施も欠かせません。シナリオベースでの訓練や障害対応の実践的な演習を実施することで、障害発生時の対応力強化につながり、被害を最小限に抑えられます。
5. まとめ
冗長構成を実現すれば、障害発生時の業務停止リスクを低減し、事業継続性を確保することが可能です。 Azure には冗長化を実現する豊富なサービスと知見があり、企業の要件に応じた柔軟な構成を支援できます。
RW では、 Azure 導入支援サービスを提供しており、要件定義から設計・構築・運用まで一貫してサポートすることが可能です。冗長化をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
Azure の導入を相談したい


資料ダウンロード
課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら
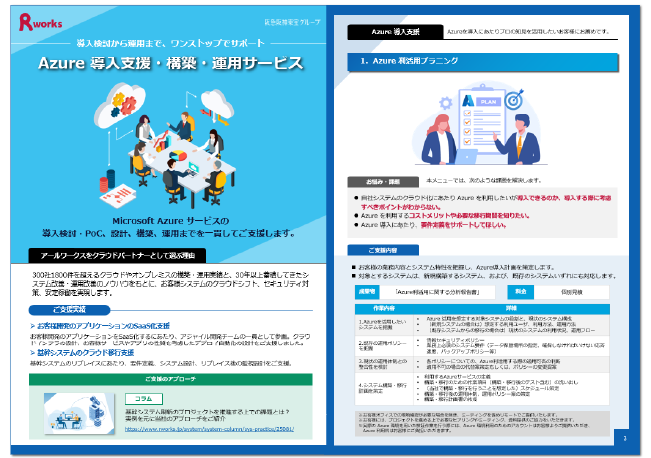
-
-
Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ
Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。
Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。
-
Microsoft Azureを利用したシステムの設計・構築を代行します。お客様のご要件を実現する構成をご提案・実装いたします。
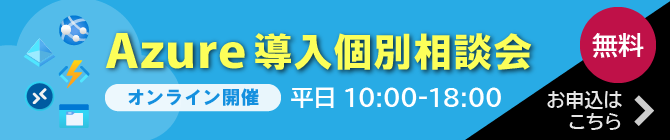
Contactお問い合わせ
お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。







 03-5946-8400
03-5946-8400